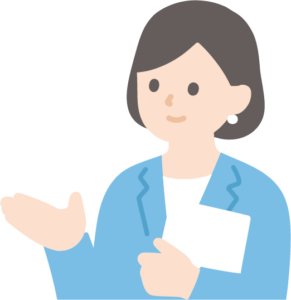人手不足の背景と、いま見直すべきこと
「なぜ、前より採用が難しいのか?」
- 求人を出しても応募が少ない。来てくれても入社までに時間がかかる。
- 入社後も、任せたい仕事までたどり着くのに手間取る
――こうした感覚は、一時的な波というより「じわじわ長く続く不足」に変わったサインです。
では、何が起きているのでしょうか。
いま、現場で起きていること
仕事は「モノを作る」だけでなく、品質の確認、設備保守、取引先への説明など、人のやり取りが欠かせない場面が増えています。
仕事が細かく分かれた結果、「この人がいれば何でも」という考え方では回りにくくなりました。
だからこそ、求める力を言葉にして伝えないと、人と仕事が噛み合いにくいのです。
もう一つは働き方の変化です。働く人の合計は増えても、1人あたりの勤務時間は短めになりがちです。家庭や学び、副業など事情は様々です。
ひと昔の前提で作られた求人(時間や場所の縛りが強い/職務が曖昧)では、応募の入口でズレを生みやすく、面接までは来ても入社や定着する前の障壁となるかもしれません。
過去の不足と、いまの不足は何が違うのか
かつての日本が経験した人手不足は、景気が良すぎて「仕事が一気に増えた」ことが主因でした。
しかし、いまは違います。サービス的な仕事が増え、働き方が多様になり、条件や段取りを合わせないと前に進まない。
求人を出せばすぐ埋まる時代ではなく、「条件を合わせ、育て、定着」してもらう設計が必要な時代に入っています。
なぜ欠員が埋まりにくいのか
まず、求職者の「生活の条件」と会社の「勤務の条件」がすれ違いがちです。
時間帯、週の出勤日数、通勤、在宅可否、学べる機会ーなどです。
次に、仕事の設計図=「何ができれば一人前か」が言葉になっていないことです。採用基準が人によってばらつき、教え方も属人的になります。期待と現実の差がストレスになり、それが離職の種になります。
さらに、中小企業ほど準備に手が回らない現実があります。
求人の言葉、育成の手順、面談の型、生活支援の段取り――どれも重要ですが、後回しになりやすい。
その結果として「経験者に限定」という一本足になり、候補者が細り、採用コストは上がるのに決まりにくい、という悪循環が起きます。
何をどう変えるのか
出発点は、「この仕事をいつまでに、どの水準で任せられる状態か?」を一文で定義することです。
これを一言で言い切れれば、入社時に必要な力と、入社後に育てていく力を分けられます。
育てる前提にするなら、「最初の90日で到達してほしい状態」を決め、週ごとの学び方と確認方法を用意します。
この時、イメージ写真・図・ショート動画は非常に効果的です。
一例として、勤務の設計は、短時間正社員や固定シフト、週4勤務など、最初から選べる形を提示します。
そして、仕事に対する評価は「覚えた→できる→任せられる」のように誰が見ても分かる基準にして、求人票・面接・入社後の指導で同じ言葉を使います。
これだけで、応募→入社→定着までの“詰まり”は目に見えて減ります。
3ポイント
・求人票に「最初の90日で身につけること」を3項目だけ明記する
・危険ポイントと品質ポイントを写真入りで掲示する。
・「困ったときの連絡カード」(担当者・連絡先・受付時間)を初日に配布する
海外人材は「最後の手段」ではなく「最初からの選択肢」に
不足が長引くほど、海外の人材を後追いで足すのは難しくなります。
仕事の段取り設計とセットで、計画の初期から組み込むことをお勧めします。
必要な日本語は安全・品質・作業指示に絞って段階設定し、手順はやさしい言葉と図で用意。
住まい・通勤・在留手続きなど生活の不安を先回りして解消しておく。
ここまでを採用設計の一部と考えると、定着も立ち上がりも安定します。
アクシスソリューションが並走できること
当社は、製造・技術分野を中心に、外国人(特にベトナム人材)のご紹介から入国までサポートします。
無料プラン「ZERO」では、候補者選定から入国までを無償で支援を行います。
採用・育てる・続けてもらうを一本の線に
いまの人手不足は、景気だけの問題ではありません。
仕事の中身と働き方が変わった結果として起きており、効く対策もまた単発ではなく設計の見直しです。
貴社では、どの職務から着手するのがいちばん効果的でしょうか。
まずは、現場の段取りをそろえるところから、ご一緒します。